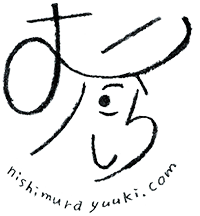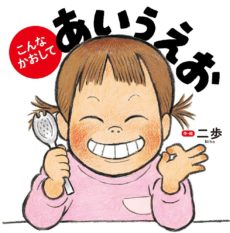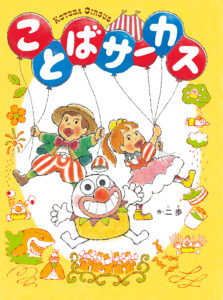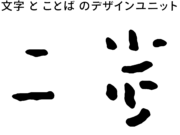人はみな「察する天才」
ことばのロボットいろはちゃん
というマンガについて。
もともと、ロボットありきで
着想したわけじゃなくて、
キャラクターは「天使」でも
「宇宙人」という設定でもよかった。
だから、AIと人間の会話の違いだけを
見せたいというわけではなくて、
別のところにも気が付いてほしい。
別のところというのは、
天才的な部分。
なんだかよくわからないが、
ものすごい処理を、一瞬で
こなしている自分(あなた)の脳を
たたえたいのかもしれないな。
*
「ポスト見てきて」
と言われたら、同時に
「手紙があったら持ってきてちょうだい」
という相手の意図を汲む。
ポスト見てきて
=手紙が来るのを期待している
=来ていたら、その手紙を読みたい
=手紙があったら持ってきてちょうだい
という具合に、
相手のことを察して、
先回りして意味を汲みとる。
ことばにならない領域で
瞬時に判断して
「言われた言葉」以上を受け取る。
(余談として…
会話は察するもの、だとしたら
言葉以前の問題として
相手の状況をみて楽しそう、かなしそう
みたいな想像が大事なのかも。
そもそも、会話は言葉でするもの
という前提に立つことが、
実はナンセンスなのでは…)
個性の時代とも言われるが、
言葉とは「同じである」ことが大事なもの。
(さらに余談だけど、
脳科学者の養老孟司 さんが言うには
個性を本当に大事にしたら皆独りぼっち。
なぜなら、他のだれにもない
自分だけのものって、
理解されないでいられるのが
本来の個性の定義だから。
正確にいうなら、
個性が大事なんじゃなくて、
個性とおぼしき領域をどれだけ
「同じ」にさせるかが大事。とのこと。)
*
そんなわけで、
「あいまいな会話は、なぜ成立するのか」
時本真吾著(岩波科学ライブラリー)
という本を、面白がって
(ものすごくゆっくり)読んでいます。
◎読むと、マンガではもっと、
「そんな過程があったのか」
というブラックボックスをのぞくような
ものがあるといいな。と思い始める。
…大げさなたとえだと、落語の
「風が吹けば桶屋が儲かる」みたいなのとか。
(↑知らない人はこちら)
こないだテレビで
「香港には三権分立がない」という
報道があった。
「三権分立があると思っていたのに」と
語る人のインタビューも。
そこでニュースは別の話題になってしまう。
はずかしながら、ぼくは
「三権分立ってなんだっけ?」レベルなので
この話題だけみても想像が及ばない。
だから何なんだっけ?と。
のちに調べたら、
三権分立がない
=国民主導ではなく、行政が主導を握る
=行政が暴挙にでたら
歯止めがきかない恐れがある
という思考過程がたとえばある。
それが何かを知っているから、
察しがつく。ということがある。
知らないと察せない。
*
◎「察する」が過剰になってしまう
ことのおもしろさも描きたい。
だれにも「好き」という言葉を
軽く使う人が、
ほとんど人から「好き」と言われた
ことがない人に、
「好き」と言ったら、
その察しは過剰になりそうだとか。
「了解です」に「!」がついていないと
それだけで、
あ、怒ってる、とか
不満にさせちゃったかな?と
過剰に察してしまったり。
察し力が天才過ぎるがゆえに
相手の意図を超えてしまうという
過程もまたぼくにとっては面白い。
*
◎「あいまいな会話は
なぜ成立するのか」っていうけど、
あいまいな会話は、
成立しないこともよくある。
「しょうゆ、こんなもんでいい」
冷ややっこにかけながらきく。
「あ、わさびわさび!」
(しょうゆはいらんけど、
それよりわさびが必要という意図)
というと、
「じゃ、もうちょっと
醤油足そうか」と。
(わさびを溶かすように
醤油のバランスをとろうという意図)
会話がなぜ伝わって、なぜ伝わらないか、
自分自身で実践できないがゆえに
そこを観察したい気持ちがあります。
2020/09/14