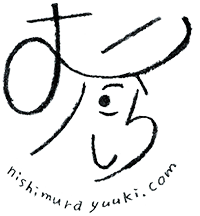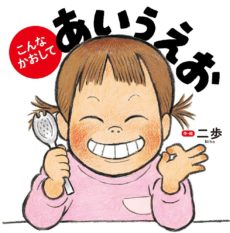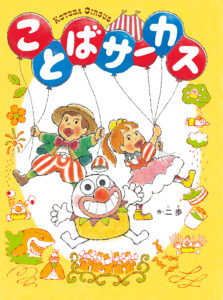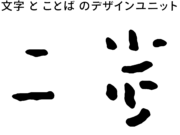ゾウをうごかすデザイン
「心のゾウを動かす方法」(扶桑社)
という本を今Audibleで聞いていて。
乳がん検診について書かれていたところが
印象的だったんだけど、
乳がんはステージ1で発見されれば
五年生存率が90%以上で、
ステージ4で見つかると、
五年生存率が39%にもなるという。
ということなので、
定期的な検診をするということが
とても大事だ、と。
それが1990年代からピンクリボン運動として
さかんになり、多くの人が認識するきっかけに
なった。
ところが、その直後に検査を受ける割合が
増えたかというと、じつはそうでもなかった
という。
(現在では、だいぶ増えているみたいですが)
つまり、知識を得ている、ということと、
実際に行動するということには
乖離がある、という話。
こころのなかにはゾウがいて、
簡単に制御はできないよ、と。
そこで、どういうふうに仕向ければ
こころのゾウが望む方に動いて
くれるんだろう、ということについて
語られているのがこの本の内容。
*
…前置きが長くなったけど、
昨日のデザイナーの鈴木千佳子さんとの
対談で聞いたことも
まさしく、こころのゾウを動かすために
デザインが存在している。ということだったと
思うんです。
*
その前までは、デザインといえば、
かわいいとか、おもしろい、とか、
「本らしく」しゃんとさせるため、
だと思っていたけど…
表紙のデザインについて聞くと
「本の内容を、
表紙というひとつのビジュアルで
的確に伝えること。」
とのことで、いままでの浅はかな自分が
恥ずかしくなってしまった。
そうだよな、ただ、かわいいだけじゃ
ないよなあ。
たしかに、
いくら自分がこれは面白い!という内容を
つくっても、その本質が表紙を見ただけで
伝わらなければ、
読んでもらう前に、読者さんのこころのゾウは
すーっと離れてしまう。
そのあたりをデザイナーの鈴木さんは
絵本の内容を読み取って
(「このかべどうする?」でいうなら)
この絵本の面白さは「えらぶこと」
「かんがえること」そして、
「かべをこえた向こうにワクワクするものが
待っている」ということ。
それを、感じてもらうためには、
どういう要素を、どういう順番で
見えるように配置すればいいのか。
と情報整理をするのだそう。
…かといって解説を加えたり、
「ここを見よ!」と注意書きをしたり、
知識を与えるようなやり方ではなくて、
こころのゾウ(感覚、直観)にどう響くか、
ということに徹底している。
(だからこそ、言語化が難しい)
実際に鈴木さんは「一対一のこころとの距離感」
という言葉で説明してくれていた。
どう感性に響かせるかという理論と、
そのための手法として
膨大な経験値に裏付けされた感覚とが
うまく織り交ざる魔法のような仕事を
される方だなと。
デザイナーさんって、
個性を消す方もいるけれど、
鈴木さんのデザインは
ちゃんと鈴木さん味がある。
ご自身でもイラスト作品を描く
というくらいなので、
自分の好きな感覚、世界の中で、
味やにおいをまとってデザインも
生まれてくる気がする。
だから、業界の中でもファンが多いんだろうな
と思う。
*
今回、色についても相談していたのですが、
それはまた明日にしよう。
2024/06/09